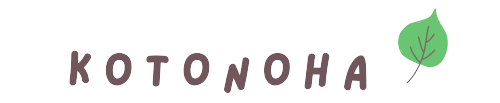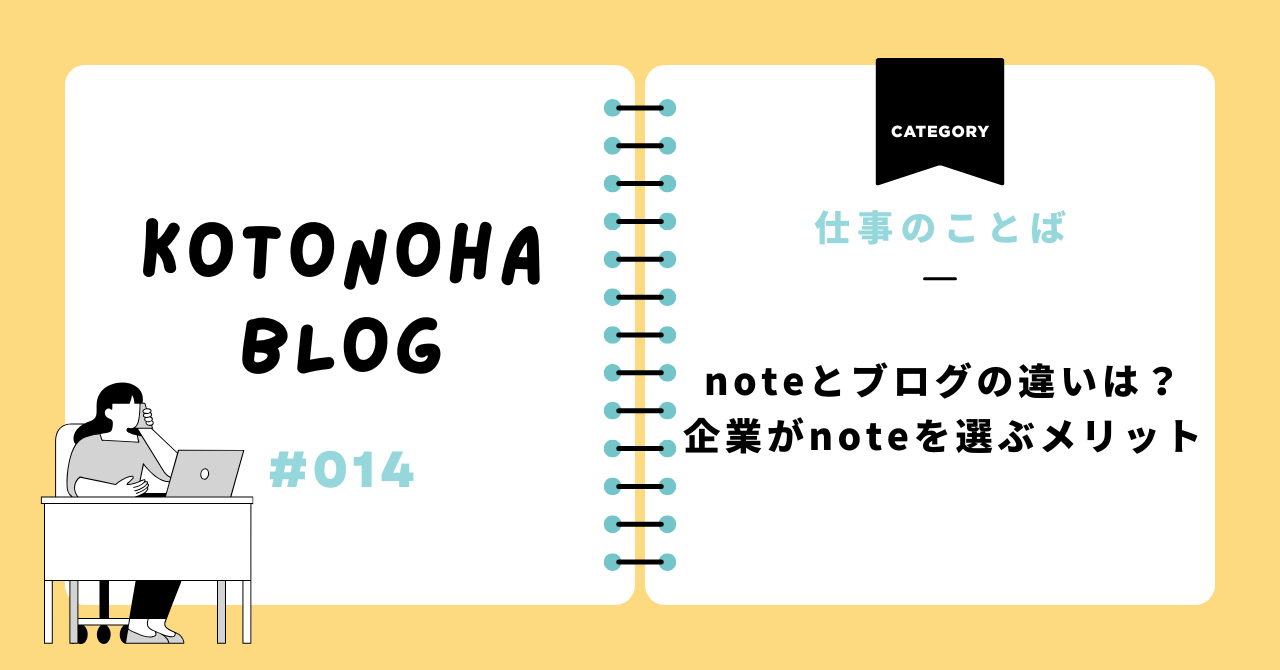「企業の情報発信にnoteとブログ、どちらを使うべき?」
オウンドメディアの運用を考えるとき、必ず出てくるこの疑問。実は、noteとブログにはそれぞれ明確な特徴があり、目的によって使い分けることが大切です。
この記事では、Webライターとして企業のコンテンツ制作に携わってきた私が、noteとブログの違いを徹底解説。企業がnoteを選ぶメリットを詳しくお伝えします。
noteとブログの基本的な違い
まず、noteとブログの基本的な違いを理解しておきましょう。
noteとは
note株式会社が運営するメディアプラットフォームです。文章・画像・音声・動画などのコンテンツを投稿でき、個人クリエイターだけでなく多くの企業も活用しています。
ブログとは
WordPressなどのCMS(コンテンツ管理システム)を使って、独自ドメインで運営するWebサイトのこと。自由度が高く、デザインや機能を自社に合わせてカスタマイズできます。
両者の最大の違いは、noteが「プラットフォーム型」、ブログが「独立型」という点です。
noteとブログの7つの違い
具体的に、どのような違いがあるのでしょうか。7つのポイントで比較してみます。
1. 始めやすさ
note:すぐに始められる
アカウント登録だけで、すぐに記事を投稿できます。サーバーやドメインの契約、サイト構築などの専門知識は一切不要。初心者でも5分あれば記事の公開が可能です。
ブログ:準備に時間がかかる
サーバー契約、ドメイン取得、WordPressのインストール、テーマ設定など、記事を書き始めるまでに複数のステップが必要。Web知識がない場合、設定だけで数日かかることも珍しくありません。
2. デザインの自由度
note:シンプルで統一されたデザイン
すべてのnote記事が同じフォーマットで表示されます。有料プランの「note pro」でもロゴやテーマカラーの変更程度で、大幅なカスタマイズはできません。ただし、このシンプルさが逆に「読みやすさ」につながっています。
ブログ:自由にカスタマイズ可能
企業のブランドイメージに合わせて、色・レイアウト・デザインを自由に設定できます。文字の装飾やボタンの配置なども思いのまま。企業らしさを出したい場合はブログが有利です。
3. 集客の仕組み
note:SNS型の集客
noteプラットフォーム内のリコメンド機能やハッシュタグ、フォロー機能があり、既存のnoteユーザーに記事を見てもらいやすい仕組みです。特にX(旧Twitter)からの流入が多く、短期間で拡散される可能性があります。
ブログ:検索エンジンからの集客
Googleなどの検索エンジンからの流入がメイン。SEO対策をしっかり行えば、中長期的に安定したアクセスが見込めます。ただし、効果が出るまでに3〜6ヶ月程度かかることが一般的です。
4. 収益化の方法
note:記事の有料販売
記事単体やマガジン(記事のまとめ)を100円〜自由な価格で販売できます。「投げ銭」機能もあり、読者から直接支援を受けることも可能。ただし、手数料として15%が差し引かれます。
ブログ:広告収入が中心
Google AdSenseやアフィリエイト広告を掲載して収益化します。アクセス数が増えれば増えるほど、広告収入も比例して増加。自由に広告を配置できるのが強みです。
5. コンテンツの方向性
note:「人」が見える発信
noteでは、書き手の人となりや考え方、体験談など「人間味のある記事」が読まれる傾向にあります。企業でも、代表や社員の想いを伝えるストーリー性のあるコンテンツが好まれます。
ブログ:問題解決型の発信
読者の悩みや課題を解決する「ハウツー記事」や「専門的な解説記事」が中心。検索意図に応える客観的な情報提供が求められます。
6. 資産性
note:プラットフォーム依存
note株式会社のサービスに依存するため、サービスが終了すれば記事も消失するリスクがあります。また、note側の規約変更によって制約を受ける可能性も。
ブログ:完全な自社資産
独自ドメインで運営するため、すべてのコンテンツが自社の資産になります。サービス終了のリスクはなく、長期的に価値を蓄積できます。
7. 分析機能
note:基本的な分析のみ
無料版では閲覧数やスキ数などの基本的な指標のみ。有料の「note pro」を導入すれば、読了率やスキ率、Google Analyticsとの連携も可能になります。
ブログ:詳細な分析が可能
Google Analyticsやサーチコンソールなど、多様な分析ツールを自由に導入できます。ユーザー行動を細かく追跡し、改善につなげやすいのが特徴です。
企業がnoteを選ぶ5つのメリット
では、企業がnoteを選ぶメリットは何でしょうか。
1. 初期コストを抑えてすぐに始められる
オウンドメディアを立ち上げる場合、通常は数十万円〜数百万円のコストがかかります。しかしnoteなら、無料アカウントですぐに情報発信を開始できます。
企業向けの「note pro」でも月額8万円程度で、独自ドメインやロゴ設定、分析機能などが利用可能。サイト構築費用と比べると、圧倒的に低コストです。
2. 既存のnoteユーザーにリーチできる
noteには既に多数のユーザーが集まっており、ハッシュタグや関連記事表示、note編集部のピックアップなど、プラットフォーム側が用意した集客の仕組みを活用できます。
ゼロから集客を始めるブログと違い、最初からある程度の読者層にアプローチできるのは大きなメリットです。
3. ブランディングに最適
noteは広告表示がなく、記事ランキングもありません。過激なタイトルで注目を集める必要がなく、企業の想いや価値観をじっくり伝えられる環境が整っています。
特に、採用広報や企業文化の発信には効果的。社員インタビューや創業ストーリーなど、企業の「人」が見えるコンテンツで共感を生み出せます。
4. SNSとの相性が良い
note記事は、XやFacebookなどのSNSで簡単にシェアできる設計になっています。記事全体だけでなく、一部の文章だけを引用してシェアすることも可能。
特にXとの相性が良く、リツイートを通じて記事が拡散されやすいのが特徴です。
5. 運用の手間が少ない
サーバー管理やセキュリティ対策、システムのアップデートなどはすべてnote側が対応。企業は記事制作だけに集中できます。
「まずはコンテンツを書くことに慣れたい」という企業にとって、noteは理想的なスタート地点になります。
noteとブログの使い分け方
では、企業はnoteとブログをどう使い分けるべきでしょうか。
noteに向いているコンテンツ
- 企業の想いやビジョンを伝える記事
- 社員・代表のインタビュー
- 事業の裏側や開発ストーリー
- 採用に関する情報
- セミナーやイベントのレポート
- 有料ノウハウ記事
ブログに向いているコンテンツ
- SEOを狙った専門的な解説記事
- 商品・サービスの詳細情報
- 導入事例・お客様の声
- 業界の最新トレンド分析
- 問い合わせや資料請求につなげる記事
「noteは読み物」「ブログは検索意図に応える情報提供」と意識すると、上手に使い分けられます。両方を運用し、noteからブログへ、ブログからnoteへと相互にリンクを張ることで、相乗効果も期待できます。
企業のnote活用事例
実際に、企業はnoteをどのように活用しているのでしょうか。成功事例を3つご紹介します。
事例1:KIRIN(キリン)
麒麟麦酒株式会社は「暮らしを軽やかに、気持ちを健やかに。」をコンセプトに運用。社員インタビューや企業文化の発信を通じて、商品の裏側にある想いや働く人の姿を伝えています。
大企業でありながら、社員一人ひとりの声を届けることで、企業の人間的な側面を見せる場として活用されています。
事例2:SHARP
シャープ株式会社は「偏愛」をテーマに、社員それぞれが愛する製品や技術への想いを発信。技術者の視点や開発秘話など、企業の「中の人」が見える記事で読者とのつながりを深めています。
関西初のnote proユーザー会を主催するなど、地域でのnote活用促進にも積極的に取り組んでいます。
事例3:ランサーズ
クラウドソーシングのランサーズは、社内&社外報マガジンとして広報・人事・総務が連携して運用。編集部名義でのインタビュー記事投稿に加え、社員個人アカウントの投稿をキュレーションしています。
企業としての発信と個人の発信を組み合わせることで、多様な視点での情報提供を実現しています。
まとめ:目的に応じて選択しよう
noteとブログは、それぞれ異なる強みを持っています。
noteがおすすめ
- すぐに始めたい、初期コストを抑えたい
- 企業の想いやストーリーを伝えたい
ブログがおすすめ
- 長期的にSEO資産を構築したい
- 自由にデザインをカスタマイズしたい
理想は、両方を運用して目的に応じて使い分けること。ただし、リソースが限られている場合は、まずnoteから始めて記事制作に慣れ、その後ブログに展開していくのもおすすめです。
大切なのは、「誰に、何を、どう届けたいか」を明確にすること。その目的に合わせて、最適なプラットフォームを選びましょう。