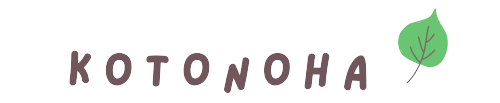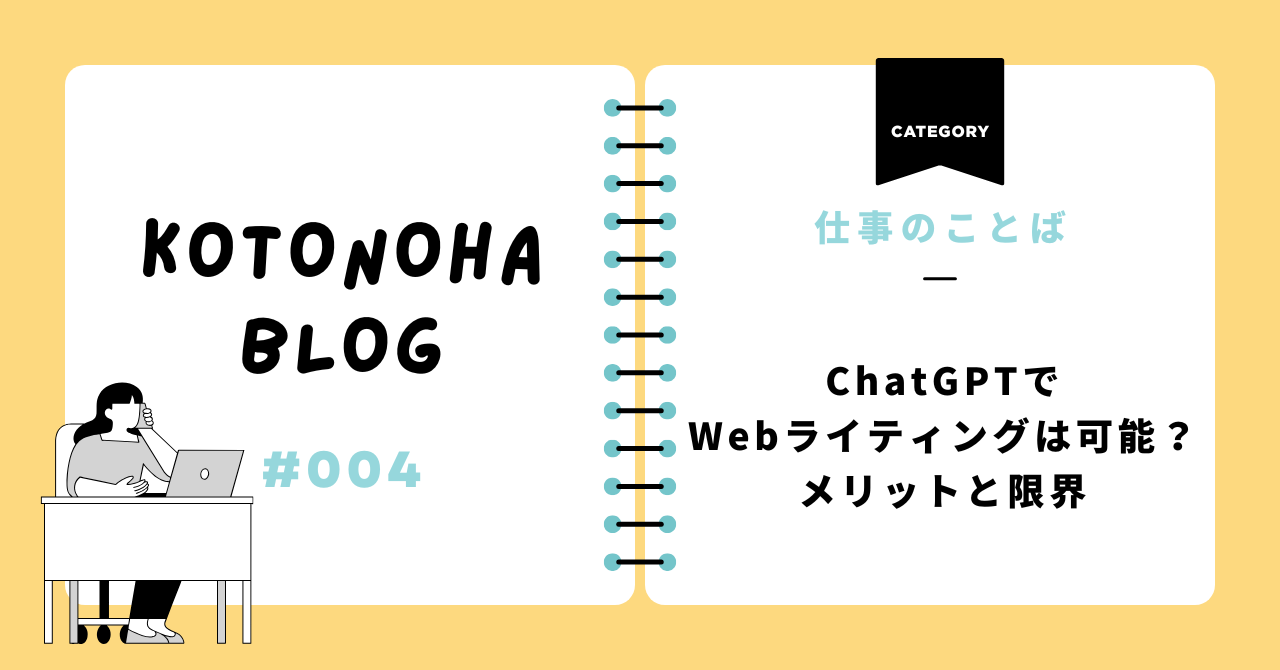「ChatGPTを使えば、ライティングがもっと楽になるのかな…」
「でも、AIに頼りすぎるのは不安…」と悩んでいませんか。
私もライター歴7年になりますが、ChatGPTが登場したときは正直、「これ、使っていいのかな」と戸惑いました。クライアントに怒られないか、記事の質が落ちないか、仕事がなくなるんじゃないか、そんな不安でいっぱいでした。
でも、実際に1年以上使い続けてわかったことがあります。それは、ChatGPTでWebライティングは可能だけど、使い方次第ということです。
この記事では、ライター歴7年の私が実際にChatGPTを使ってわかったメリットと限界、そして効果的な使い方を正直にお伝えします。
ChatGPTでWebライティングは可能、でも「使い方次第」
まず結論から言うと、ChatGPTを使ったWebライティングは可能です。ただし、「コピペして終わり」では絶対にダメです。
ChatGPTはあくまで「補助ツール」。リサーチや構成案作成、アイデア出しには非常に便利ですが、最終的な文章は自分で書くか、しっかり編集する必要があります。
私自身、ChatGPTを使うようになってから、記事作成の時間が大幅に短縮されました。でも、それは「丸投げ」したからではなく、「効率化できる部分だけChatGPTに任せた」からです。
実際に使ってわかったメリット5つ
ここからは、実際にChatGPTを使ってみて感じたメリットをお伝えします。
構成案作成が圧倒的に早い
記事の構成を考えるとき、ChatGPTは本当に便利です。
以前は、記事の見出しを考えるだけで30分以上かかることもありました。でも今は、ChatGPTに「〇〇というテーマで、3000文字の記事構成を作って」と頼めば、数秒で複数のパターンを提案してくれます。
そこから良いものを選んで、自分でブラッシュアップすればOK。構成案作成の時間が大幅に短くなりました。
リサーチの効率化ができる
記事を書く前のリサーチにも、ChatGPTは役立ちます。
たとえば、「つみたてNISAのメリット・デメリットを教えて」と聞けば、基本的な情報をまとめてくれます。もちろん、その情報は必ず公式サイトなどで確認しますが、「何を調べればいいか」の当たりをつけるのに便利なんです。
リサーチの初期段階で使うことで、時間の効率化が図れます。
言い回しのバリエーションが増える
同じ内容を違う表現で書きたいとき、ChatGPTが助けてくれます。
たとえば、「この文章を、もっとカジュアルに言い換えて」「別の言い回しを3つ提案して」と頼めば、複数のパターンを出してくれます。自分では思いつかなかった表現に出会えることも多いんです。
表現の幅を広げるという意味で、ChatGPTは良いアイデアの引き出しになっています。
アイデア出しに使える
「記事のネタが思いつかない…」というとき、ChatGPTにブレストしてもらうのもおすすめです。
「〇〇に関する記事のテーマを10個考えて」と頼めば、いろんな切り口を提案してくれます。その中には「それは違うな」というものもありますが、「この切り口、面白いかも」というヒントが見つかることも。
アイデア出しの壁打ち相手として、ChatGPTは優秀です。
推敲の補助になる
記事を書き終えた後、ChatGPTに「この文章をもっと読みやすくして」と頼むこともあります。
自分では気づかなかった回りくどい表現や、わかりにくい部分を指摘してもらえることがあります。ただし、ChatGPTの提案をそのまま採用するのではなく、「こういう視点もあるのか」と参考にする程度です。
推敲の際の第三者の目として、使える場面があります。
ChatGPTをライティングで使用する限界5つ
便利なChatGPTですが、もちろん限界もあります。ここでは、実際に使ってみて感じた「ここはダメだな」というポイントをお伝えします。
最新事情や細かなニュアンスまでは拾いきれない
ChatGPTは学習データに基づいて回答するため、最新の情報には対応できていないことがあります。
たとえば、法改正や制度変更、最新のトレンドなどは、正確な情報が得られないことも。「2023年に〇〇が改正された」といった情報も、実際には時期が違っていたり、内容が古かったりすることがあります。
特に金融や法律、制度に関する記事を書くときは、ChatGPTの情報を鵜呑みにせず、必ず公式サイトで最新情報を確認することが大切です。
プロンプトが曖昧だと「どこにでもある文章」になってしまう
ChatGPTは、一般的な情報を整理して伝えるのは得意ですが、指示(プロンプト)が漠然だと、ありきたりでオリジナリティに欠けた文章になりがちです。
工夫すれば、文章のトーンや切り口を変えることはできます。でも、「3人の子育てをしながらライターをしている私だから伝えられること」や「実際に失敗して学んだこと」といったリアルな体験は、AIには書けません。
読者が知りたいのは「誰が書いても同じ情報」ではなく、「その人だからこそ書ける内容」です。失敗から学んだことや試行錯誤のプロセスなどは、自分の言葉で書くことが大切です。
専門分野になるほど、情報が表面的になりやすい
ChatGPTは幅広い知識を持っていますが、深い専門性には弱いです。
たとえば、私は金融ライターとして働いていますが、ChatGPTが出す金融系の情報は表面的なものが多いんです。実務経験者だからこそわかる細かいニュアンスや、最新の制度変更については、自分で調べて書く必要があります。
専門性が求められる記事では、ChatGPTだけでは不十分だと感じています。
感情表現が弱く、心に響きにくい
ChatGPTは論理的で整理された文章を書くのは得意ですが、感情に訴える文章は苦手です。
たとえば、「転職に悩んでいる人に寄り添う記事」を書くとき、ChatGPTは一般的なアドバイスを並べますが、「その気持ち、わかります」という共感や、「私も同じ経験をしました」という温度感は出せません。
読者の心を動かす文章を書きたいなら、自分の声や感情を込めて書くことが欠かせません。
ChatGPTを使った実際のライティング手順
ここでは、私が実際にChatGPTを使って記事を書くときの流れを、ステップごとに紹介します。
ステップ1:テーマとターゲットを決める
まず、記事のテーマと想定読者を明確にします。これはChatGPTに頼らず、自分で考えます。
例:
- テーマ:「つみたてNISAの始め方」
- ターゲット:「投資初心者の30代会社員」
- 記事の目的:「つみたてNISAを始める具体的な手順を知ってもらう」
ここをしっかり決めておくと、ChatGPTへの指示も明確になります。
ステップ2:ChatGPTで構成案を作る
テーマが決まったら、ChatGPTに構成案を考えてもらいます。
たとえば「つみたてNISAの始め方について、投資初心者向けの3000文字の記事構成を作ってください。見出しは5〜7個程度でお願いします」と依頼すると、すぐにたたき台が出てきます。
出力された構成をベースに、不要な部分を削ったり、足りない部分を加えたりして調整しましょう。複数パターンを出してもらい、良いところを組み合わせるのもおすすめです。
また、「〇〇という記事の見出しを5パターン考えて」と頼めば、見出しの候補もすぐに作れます。ChatGPTの見出しは少し硬かったり平凡だったりすることがあるので、最後に自分らしい表現に直すのがポイントです。
ステップ3:リサーチする
構成案ができたら、各見出しに必要な情報を調べていきます。
たとえば「つみたてNISAのメリット・デメリットを教えて」と聞いて、基本情報を把握します。ただし、必ず公式サイトや信頼できる情報源で確認します。
金融庁のサイトや証券会社の公式情報など、一次情報を確認することが大切です。ChatGPTはあくまで「リサーチの出発点」として使い、そこから自分で深掘りしましょう。
ステップ4:自分の言葉で執筆する
リサーチが終わったら、自分の言葉で記事を書きます。
ここが最も重要なポイントです。ChatGPTに「記事を書いて」と丸投げするのではなく、自分で文章を書きます。ChatGPTはあくまでアイデアや言い回しのヒントとして活用しましょう。
体験談や具体例を入れると、オリジナリティのある記事になります。執筆中に表現に迷ったときは、「この文章をもっとカジュアルに言い換えて」「別の言い回しを3つ提案して」などのプロンプトで頼むのも有効です。その中から自分に合う表現を取り入れることで、文章にバリエーションを加えられます。
ステップ5:ChatGPTで表現を磨く
記事を書き終えたら、部分的にChatGPTを使って表現を磨きましょう。
完成した文章をそのまま提出するのではなく、「この文章の改善点を教えて」と聞くことで、回りくどい表現やわかりにくい部分を指摘してもらえます。
ただし、ChatGPTの提案をそのまま使うのではなく、「なるほど、この部分はもっとわかりやすくできるな」と気づきを得る程度に活用するのがポイントです。自分の手で修正することで、文章のクオリティをしっかり高められます。
ステップ6:事実確認と最終チェック
最後に、もう一度記事全体を読み直します。
- 事実関係に間違いはないか
- 数字や固有名詞は正確か
- AI臭い表現が残っていないか
- 文章の流れは自然か
- 読者に伝わる内容になっているか
この流れで記事を作成すると、ChatGPTの便利さを活かしつつ、オリジナリティのある記事が書けます。
まとめ:ChatGPTは敵じゃなく味方
ChatGPTは、使い方次第でWebライティングを強力にサポートしてくれるツールです。大切なのは「丸投げする」のではなく、あくまで補助ツールとして使いこなすことです。
リサーチや構成案作成はChatGPTに任せつつ、最終的な文章は自分の言葉で書く。この使い分けができれば、効率も質もぐっと上がります。
私自身、ChatGPTを使い始めてから記事作成の時間は短縮されましたが、それは丸投げしたからではなく、効率化できる部分だけChatGPTに任せたからです。
ChatGPTは敵ではなく、ライティングを助けてくれる味方です。怖がらずに、少しずつ自分なりの使い方を見つけていけたらいいですね。