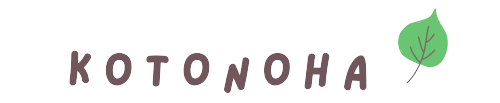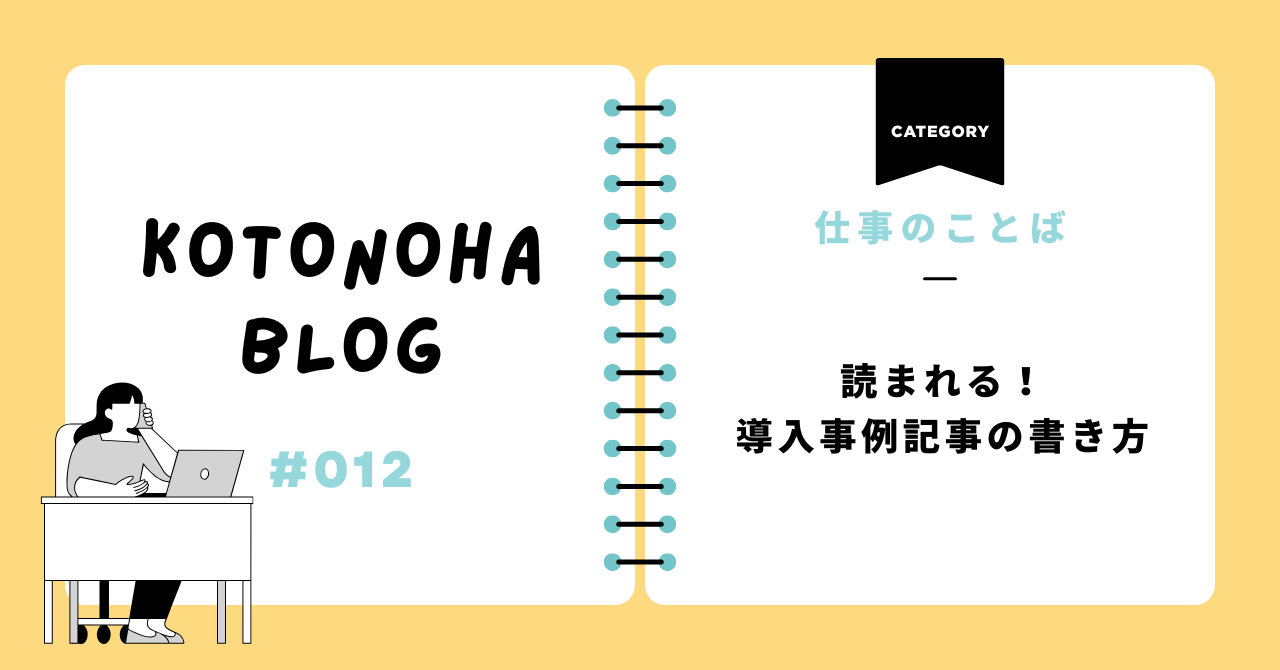企業のオウンドメディアやサービスサイトで、近年ますます需要が高まっている「導入事例記事」。BtoB企業を中心に、顧客獲得の重要なコンテンツとして注目されています。
でも、「導入事例って何を書けばいいの?」「インタビューで何を聞けばいいかわからない」と悩んでいるライターの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、インタビューライターとして数多くの導入事例記事を執筆してきた経験から、効果的な導入事例記事の書き方を詳しく解説します。
導入事例記事とは?なぜ今求められているのか
導入事例記事とは、企業の製品やサービスを実際に導入した顧客の声を紹介するコンテンツです。
導入事例が重要な理由は3つあります。
まず、購買検討段階にある見込み客に対して、実際の利用シーンをイメージしてもらえること。カタログやサービス紹介ページでは伝わりにくい「リアルな使用感」や「具体的な成果」を届けられます。
次に、第三者の声だからこそ説得力が高いこと。企業が自社製品を「素晴らしい」とアピールするよりも、実際の利用者が「こんな効果があった」と語るほうが、圧倒的に信頼されます。
そして、SEO効果が高いこと。「製品名 + 導入事例」「業界名 + 課題解決」など、購買意欲の高いキーワードで検索上位を狙えます。
導入事例記事の基本は「課題解決型」
導入事例記事には、大きく分けて2つのパターンがあります。
- 課題解決型: 課題→導入→解決の流れで書くスタンダードな形式
- 比較検討型: なぜ他社製品ではなくこれを選んだかに焦点を当てた形式
どちらの型を選ぶかは、クライアントの状況や商材の特性によって変わります。
新規開拓を狙うなら課題解決型、競合からの乗り換えを促進したいなら比較検討型が効果的です。迷ったときは汎用性の高い課題解決型を選んでおけば間違いありません。
この記事では、最も汎用性の高い「課題解決型」の書き方を中心に説明していきます。
効果的な導入事例記事の5つの構成ポイント
課題解決型の導入事例記事は、次の5つのパートで構成するのが基本です。
1. 現在の事業と業務
まず、取材先企業の事業内容や、インタビュー対象者の部署・役職・担当業務を紹介します。
ここでのポイントは、クライアント企業の狙いに合わせた書き方をすること。
たとえば、同じ業界への展開を強化したいクライアントなら、事業の特徴や業界特有の課題を丁寧に書き込みます。
経営層向けに訴求したいなら役職者の視点を、現場の担当者向けなら実際の業務内容を詳しく描写する、といった具合です。
単なる企業紹介ではなく、「このあとの課題や成果がより響くように」という意図を持って書きましょう。
2. 導入前に抱えていた課題
導入事例の成否を分けるのが、この「課題」のパートです。
ここで大切なのは、読者に「わかる、わかる!」と共感してもらうこと。
ドラマチックに盛り上げようとして、大げさに深刻な課題を書く必要はありません。むしろ、「ちょっとしたことだけど、現場では地味にストレスになっている」という課題のほうが、多くの読者に刺さります。
ただし、取材先の信用を損なうような書き方は絶対にNG。機密情報や失敗談を赤裸々に書きすぎると、取材先企業の評判を落としかねません。
「共感」と「配慮」のバランスを取りながら、次の「解決策の模索」へと自然に読み進めてもらえる流れを作りましょう。
3. 解決策の模索
課題を解決するために、どんな製品やサービスを検討したのか。どのように情報を集め、何と比較したのかを書くパートです。
実は、この記事を読んでいる見込み客の多くは、まさに今この段階にいます。だからこそ、ここで「自分と同じだ」と感じてもらえると、記事への没入度が一気に高まります。
注意すべきは、競合製品の悪口は絶対に書かないこと。
たとえば取材中に「A社の製品は使いにくくて」という話が出ても、そのままは書きません。「以前使用していた製品には○○の機能がなく、工数がかかっていました」といった、事実ベースの表現にとどめます。
競合を下げることでクライアント製品を持ち上げるのではなく、困っていた状況を淡々と伝えるだけで充分です。
4. 製品・サービスの導入
導入を決めてから、実際に使いこなせるようになるまでのプロセスを書きます。
BtoB商材の場合、「買ったらすぐ使える」製品ばかりではありません。システム連携の苦労、カスタマイズの手間、社内への浸透など、導入時には必ず何かしらの壁があります。
ここでは、読者の「本当に使いこなせるかな?」という不安を先回りして解消することが目的です。
もしトラブルがあったなら、どんなサポートを受けて乗り越えたのかを具体的に書きましょう。逆に、スムーズに導入できたなら、「こんなに簡単でした」というポイントをアピールします。
カタログに「手厚いサポート」と書いてあっても、それだけでは何も伝わりません。実際のエピソードを通じて、具体的なサポート体制を見せることが重要です。
5. 導入後の効果
導入事例のクライマックスです。製品導入によって、何がどれだけ改善されたのかを明確に示します。
ここで絶対に聞き出したいのが「数字」です。
- コストが何パーセント削減されたのか
- 作業時間が何時間短縮されたのか
- 売上が何パーセント向上したのか
具体的な数値があると、記事の説得力が段違いに高まります。
もし「まだ数値は出ていなくて…」と言われても、諦めずに「体感として半分くらいですか? 3分の1くらいですか?」と食らいついてみましょう。
また、成果の書き方はターゲット読者に合わせることも重要です。
たとえば「残業時間が3分の1に減った」という成果を書くとき、
- 現場の担当者向けなら「早く帰れるようになった」
- 中間管理職向けなら「部の残業削減目標を達成できた」
- 経営層向けなら「削減コストを新規投資に回せるようになった」
と、同じ成果でも響く書き方が変わります。
プラスα:今後の展望
記事の締めとして、「今後どう活用していきたいか」「新たに挑戦したいこと」を聞いてみましょう。
ここで良い話が出たら記事に盛り込めますし、出なければ「5. 導入後の効果」で締めても問題ありません。
ときには、ここで語られた展望が、クライアント企業の次の新製品につながることも。そんなときは自然に次の製品紹介へ誘導できるような締め方を提案してみましょう。
インタビューで成果を引き出す3つのコツ
ここからは、実際の取材現場で使えるテクニックを紹介します。
コツ1:「なぜ」を3回繰り返す
「便利になりました」という回答には、「具体的にどんな場面で便利だと感じますか?」「それまではどうしていたんですか?」「なぜその方法だと不便だったんですか?」と深掘りしていきます。
表面的な回答の奥にある、具体的なエピソードや感情を引き出すことで、記事に深みが生まれます。
コツ2:失敗談こそ宝物
「導入時にうまくいかなかったこと」「最初は使いこなせなかったこと」といった失敗談は、実は記事を面白くするうえで欠かせません。
完璧すぎる成功談よりも、「最初は苦労したけど、サポートのおかげで乗り越えられた」というストーリーのほうが、読者に親近感を与えます。
コツ3:沈黙を恐れない
質問に対して相手が考え込んでしまったとき、つい助け舟を出したくなりますが、少し待ってみましょう。
その沈黙の後に、本音や具体的なエピソードが出てくることが多いのです。
実例で見る:導入事例記事のビフォー・アフター
実際に私が執筆した導入事例記事を例に、どのように改善したかをご紹介します。
ケース1:クラウド会計ソフトの導入事例
【Before】初稿の段階で出てきた内容
「紙での管理が大変でした。このソフトを導入して、業務が効率化されました。今では経理作業がとても楽になっています。」
この状態では、具体性に欠け、読者の共感も得られません。
【After】追加取材と構成調整後
「月末になると、各部署から上がってくる経費精算の紙の山に埋もれていました。手書きの領収書を1枚ずつ確認し、Excelに手入力。1件あたり平均3分かかり、月間300件を処理するだけで15時間。締め日前は毎晩21時まで残業が続いていました。
クラウド会計ソフト導入後は、スマホで領収書を撮影するだけでデータ化。手入力の時間が月間2時間まで短縮され、経理担当の残業時間は70%削減されました。『子どものお迎えに間に合うようになった』と、現場からも喜びの声が上がっています。」
改善ポイント:
- 具体的な数字を追加(15時間→2時間、70%削減)
- 業務の臨場感を描写(「紙の山に埋もれる」)
- 導入者の感情や生活の変化まで言及
このように、同じ「業務効率化」という成果でも、書き方次第で読者への響き方が大きく変わります。
ケース2:採用管理ツールの導入事例
【Before】表面的な回答
「応募者の管理が煩雑でした。このツールで一元管理できるようになり、採用業務がスムーズになりました。」
【After】課題と成果を具体化
「面接日程の調整メールだけで1日2時間を費やしていました。応募者が100名を超えると、誰にいつ返信したか、次の選考ステップは何かを把握するだけでも一苦労。『あの人、どこまで進んでたっけ?』とメールを遡る日々でした。
採用管理ツール導入後は、応募者の状況が一目で可視化され、メールテンプレート機能で日程調整も自動化。調整業務にかかる時間は1日30分に短縮され、浮いた時間を面接準備や応募者とのコミュニケーションに充てられるようになりました。結果、内定承諾率が前年比15%向上しています。」
改善ポイント
- 困っていた具体的な場面を描写
- 担当者の心の声を入れる(「あの人、どこまで…」)
- 時間短縮だけでなく、その先の成果(内定承諾率向上)まで追加
数字の改善だけでなく、その先にある「人の変化」まで書くことで、導入後の未来が具体的にイメージできる記事になります。
よくある失敗パターンと対処法
失敗1:課題が浅すぎる
「業務効率化したかった」だけでは、読者に刺さりません。「具体的にどんな作業に何時間かかっていたのか」「それが現場にどんな負担だったのか」まで聞き出しましょう。
取材では「たとえば、先月の繁忙期だと、その作業に何時間くらいかかりましたか?」といった具体的な数字を引き出す質問を心がけています。
失敗2:成果が抽象的
「すごく良くなりました」では記事になりません。数字、具体例、誰がどう感じているか、といった要素で肉付けしていきます。
「何がどれくらい改善されましたか?」「現場の方はどんな反応でしたか?」と複数の角度から深掘りすることで、読者がイメージしやすい成果を描けるようになります。
失敗3:企業のPRになりすぎる
導入事例は広告ではなく、読者にとって有益な情報であるべきです。「この製品、最高です!」だけでなく、「どう使いこなしたか」「どんな工夫をしたか」まで書くことで、読者の参考になる記事になります。
「導入時に工夫したこと」「社内でどう浸透させたか」といった、読者が真似できるノウハウを盛り込むことを意識しましょう。
導入事例記事の執筆を外注するメリット
ここまで読んで「導入事例って思ったより難しそう」と感じた方もいるかもしれません。
実は、多くの企業が導入事例の執筆を次のような理由から外部のライターに依頼しています。
- 客観的な視点で書ける
- インタビュー経験があるライターなら、取材から執筆までスムーズ
- SEOを意識した構成で、検索流入を増やせる
- 社内リソースを節約できる
特に、インタビュー経験のあるライターに依頼すると、取材時に本音や具体例を引き出すスキルがあるため、読み応えのある記事に仕上がります。
まとめ:導入事例記事で成果を出すために
導入事例記事は、見込み客の購買を後押しする強力なコンテンツです。
成功の鍵は、5つの構成をしっかり押さえること。そして何より、読者に「自分ごと」として読んでもらえる共感ポイントを作ることです。
取材では表面的な回答に満足せず、「なぜ」を繰り返し、具体的なエピソードや数字を引き出しましょう。
導入事例記事の執筆やインタビュー取材でお困りのことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。あなたの製品・サービスの魅力を、顧客の声を通じて最大限に引き出すお手伝いをいたします。