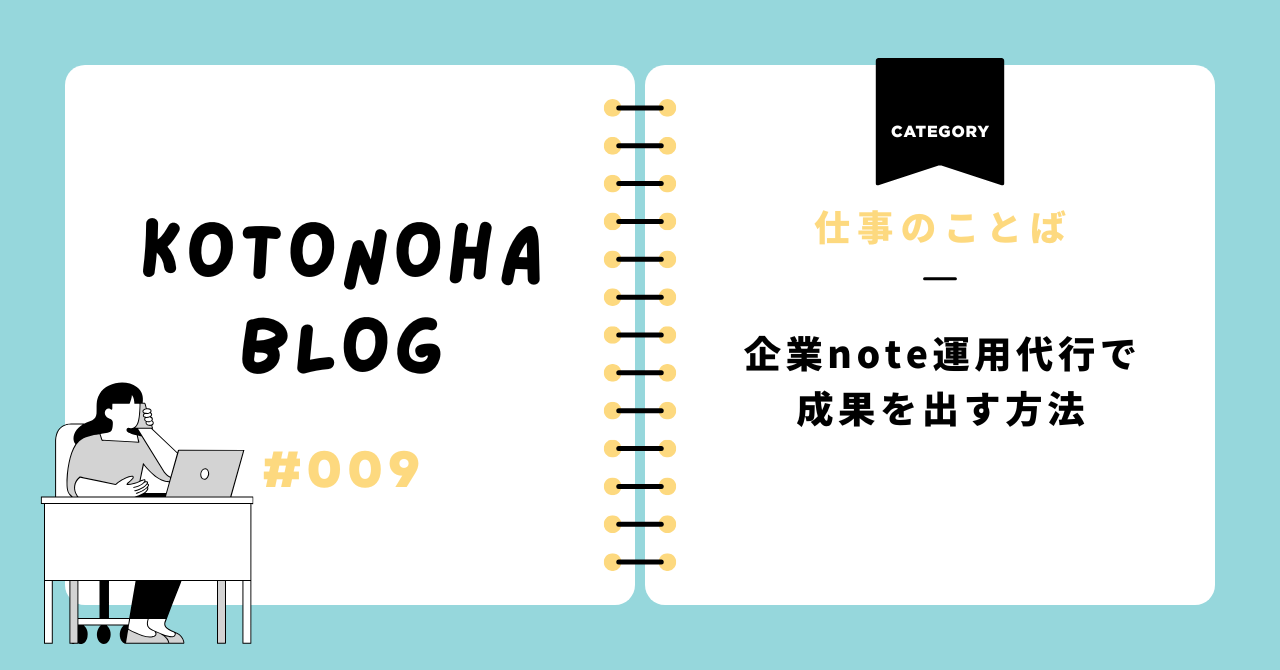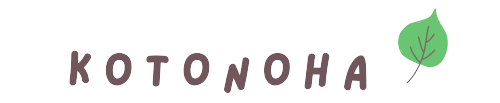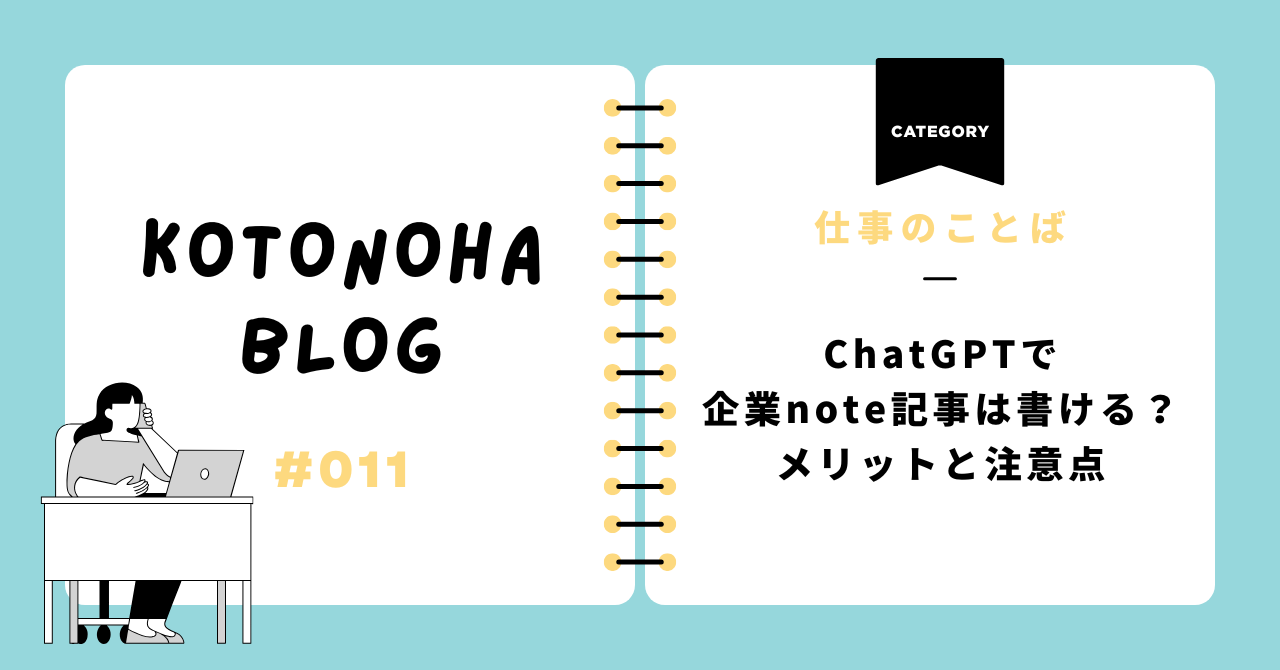「ChatGPTを使えば、企業noteの記事も簡単に書けるんじゃないか」
「でも、AIが書いた記事で本当に大丈夫なのかな…」
そんな疑問を持つ方も多いでしょう。
私も最初は半信半疑でしたが、実際に使ってみて「便利な部分」と「人の手が必要な部分」の両方を実感しました。
結論から言うと、ChatGPTは企業note作成の強力なサポートツールになります。でも、AIだけで完結させるのは危険です。
この記事では、実際にChatGPTを使って企業note記事を書いた経験をもとに、メリットと注意点を正直にお伝えします。
ChatGPTで企業note記事は書けるのか
まず結論からお伝えします。
ChatGPTで企業note記事は書けます。でも、そのまま使うのは危険です。
AIが生成した文章をベースに、人間が手を加えることで、質の高い企業note記事を効率的に作ることができます。
実際に使ってみてわかったこと
私が企業note記事の作成にChatGPTを使ったとき、最初は「こんなにスムーズに書けるんだ!」と驚きました。
構成案や下書きがすぐに書けて、30分かかっていた作業が10分に。
でも、生成された文章をそのまま読んでみると、
- 企業のトーンと合わない
- 表現が一般的すぎて個性がない
- 事実確認が必要な箇所がある
- 「企業が本当に伝えたいこと」が抜けている
結局、手直しに時間をかけて、ようやく「これなら出せる」という記事になりました。
AIは確かに便利ですが、「人の手」が欠かせない。これが、実際に使ってみて感じた正直な感想です。
ChatGPTを企業note作成に使うメリット
では、具体的にChatGPTはどんな場面で役立つのか。実際に使ってみて感じたメリットをお伝えします。
構成案と下書きを素早く作れる
企業note記事を書くとき、「どんな構成にしようか」と悩むことがあります。ChatGPTに構成案を依頼すると、数秒で提案してくれます。
たとえば、「新しい福利厚生制度の導入について」という記事であれば、
プロンプト例:
「新しい福利厚生制度の導入について、企業noteの記事構成を考えてください。読者は求職者です。」以下のような構成案が返ってきます。
- 導入:なぜこの制度を導入したのか
- 制度の概要
- 社員の声
- 会社の想い
- まとめ
この構成をベースに、企業の実情に合わせて調整すれば、記事の骨組みが完成。構成が決まったら、そのままChatGPTに下書きを書いてもらいます。
プロンプト例:
「以下の構成で、企業note記事の下書きを書いてください。トーンはフランクで親しみやすく。
[構成をコピペ]」数千文字の下書きが一気に生成されます。
あとは企業のエピソードを追加して、トーンを調整するだけ。「真っ白な画面に向かって、何を書こう…」という時間がなくなるだけで、作業効率が大きく変わります。
複数のパターンを試せる
ChatGPTのいいところは、何度でもやり直せることです。
「もっとカジュアルに」「もっとフォーマルに」「導入部分を変えて」と指示を出せば、別のバージョンを生成してくれます。
人間が複数パターンを書くのは時間がかかりますが、AIなら数秒です。
複数のパターンを比較して、一番良いものを選ぶ。この使い方ができるのは、AIならではのメリットです。
アイデア出しに使える
「社員インタビュー記事で、どんな質問をすればいいか」
「会社の取り組みを記事にするとき、どんな切り口があるか」
こういったアイデア出しにも、ChatGPTは役立ちます。
プロンプト例:
「社員インタビュー記事で、求職者が知りたいと思う質問を10個考えてください。」すると、質問のアイデアがずらっと並びます。
その中から良いものを選んだり、組み合わせたりすることで、インタビューの質問リストが完成します。
アイデアの壁打ち相手として、ChatGPTはとても優秀です。。
ChatGPTで企業note記事を書くときの注意点
便利なChatGPTですが、企業note作成では特に注意すべき点があります。
企業のトーンが出ない
ChatGPTが生成する文章は、一般的で無難です。
でも、企業noteでは「その企業らしさ」が大切です。
ベンチャー企業のフランクなトーン、老舗企業の丁寧なトーン。企業によって、求められる文体は全然違います。
ChatGPTに「フランクに書いて」と指示しても、本当にその企業らしいトーンになるとは限りません。
私が実際に使ったときも、「なんか違う」と感じることが多かったです。企業の温度感を理解して、文章を調整する。これは、人間にしかできない仕事です。
ファクトチェックが必須
ChatGPTは、事実と異なる情報を生成することがあります。
特に、企業の具体的な制度や数字、実績については、AIが勝手に「それらしい内容」を作ってしまう危険があります。
企業noteは、企業として発信する公式な情報です。一つの間違いが、企業の信頼を損なうことになりかねません。
AIが生成した内容は、必ず人間が確認する。これは絶対のルールです。
数字や固有名詞、制度の内容、実績。これらは全て、クライアントに確認するか、公式な資料と照らし合わせる必要があります。
表面的な内容になりがち
ChatGPTは一般的な情報をもとに文章を生成するため、「誰でも書けそうな、表面的な内容」になりがちです。
でも、企業noteで大切なのは、「その企業ならではのエピソード」や「社員の生の声」です。
私が会社の取り組みを記事化したときも、ChatGPTが生成した下書きは「一般論」でした。
「なぜこの取り組みを始めたのか」「実際にどう変わったのか」といった、企業特有のストーリーは、ヒアリングを通じて人間が引き出す必要があります。
AIはあくまで「土台」を作るツール。その上に、人間が「企業らしさ」を積み上げていくイメージです。
コンプライアンスリスク
企業として発信する以上、コンプライアンス意識は欠かせません。
ChatGPTは、社会的な配慮や企業ルールを完全に理解しているわけではありません。そのため、知らず知らずのうちに、社会的に配慮が必要な表現や企業として避けるべき言い回しが含まれてしまう可能性があります。
AIが生成した文章は、必ずコンプライアンスの観点でチェックする必要があります。
「これ、書いて大丈夫かな?」と迷ったら、必ずクライアントに確認しましょう。
ChatGPTを企業note作成に使う具体的な方法
では、実際にどうやってChatGPTを企業note作成に活用すればいいのか。私が実践している方法をお伝えします。
ステップ1:構成案を作ってもらう
まず、記事のテーマとターゲット読者を明確にして、ChatGPTに構成案を考えてもらいます。
プロンプト例:
「〇〇について、企業note記事の構成案を考えてください。
読者は△△です。記事の目的は□□です。」生成された構成案を見て、足りない部分を追加したり、順番を入れ替えたりします。
ステップ2:下書きを生成してもらう
構成が決まったら、下書きを書いてもらいます。
プロンプト例:
「以下の構成で、企業note記事の下書きを書いてください。
トーンは〇〇。文字数は△△字程度。
[構成をコピペ]」この時点では、完璧な文章を求めません。あくまで「土台」として使います。
ステップ3:企業の情報を追加する
ChatGPTが生成した下書きに、企業特有の情報を追加します。
- 社員のエピソード
- 具体的な数字や実績
- 企業の想いや背景
- 社内で実際に使われている言葉
この「企業らしさ」を加えることが、一番大切な作業です。
ステップ4:トーンを調整する
企業の温度感に合わせて、文体を調整します。
- もっとカジュアルに
- もっとフォーマルに
- もっと温かみのある表現に
企業のトーンを掴んで、文章を磨いていきます。
ステップ5:ファクトチェック
最後に、事実確認を徹底します。
- 数字は正確か
- 固有名詞は正しいか
- 制度の内容は間違っていないか
- コンプライアンス的に問題ないか
この確認作業を怠ると、企業の信頼を損なうリスクがあります。必ず人間がチェックしましょう。
ChatGPTを使うべき場面・使わない方がいい場面
ChatGPTは便利ですが、すべての場面で使うべきではありません。
ChatGPTを使うべき場面
以下のような場面では、ChatGPTが役立ちます。
- 記事構成を考えるとき
- 下書きやたたき台を作るとき
- 文章を別の表現に言い換えるとき
- タイトルや切り口のアイデアを出したいとき
これらは、AIが得意とする作業です。効率化できる部分は、積極的にAIに任せましょう。
ChatGPTを使わない方がいい場面
一方、以下のような場面では、AIに頼らない方がいいです。
- 社員や内定者など「人の声」を扱うインタビュー記事
- 企業独自のストーリーや内部情報を含む記事
- 事実確認や表現チェックが必要な最終段階
- 企業らしいトーンや温度感を整えるとき
AIと人間、それぞれの得意分野を理解して、使い分けています。
企業noteでAIを使うときの心構え
ChatGPTを企業note作成に使うときは、以下の心構えが大切です。
AIは「サポートツール」
構成案を作る、下書きを生成する、アイデアを出す。こういった作業をAIに任せることで、時間を効率的に使えます。
でも、企業の想いを引き出すこと、読者に届く言葉に翻訳すること、企業らしいトーンに仕上げること。これらは、人間にしかできない仕事です。
効率化できる部分はAIに任せて、人間にしかできない部分に時間を使う。この考え方が、AIとの賢い付き合い方です。
責任は人間が負う
AIが生成した文章でも、最終的な責任は人間にあります。
事実誤認、コンプライアンス違反、炎上リスク。これらは全て、人間がチェックして防ぐ必要があります。
「AIが書いたから」は、言い訳になりません。人間が最終責任を負う。この意識を忘れないように常に心がけています。
ChatGPTと企業noteライティングの未来
AIライティング技術は、これからもどんどん進化していきます。
でも、企業noteに関しては、AIだけで完結することはないと思います。
なぜなら、企業noteで大切なのは、「その企業ならではの声」を伝えることだからです。
社員の想い、企業の背景、現場のリアルな声。これらは、ヒアリングを通じて人間が引き出し、文章にしていきます。
AIは効率化のためのツール。人間は、企業の想いを引き出し、読者に届けるための橋渡し役。
この役割分担を理解して、AIと上手に付き合っていくことが、これからの企業noteライターに求められるスキルだと思います。
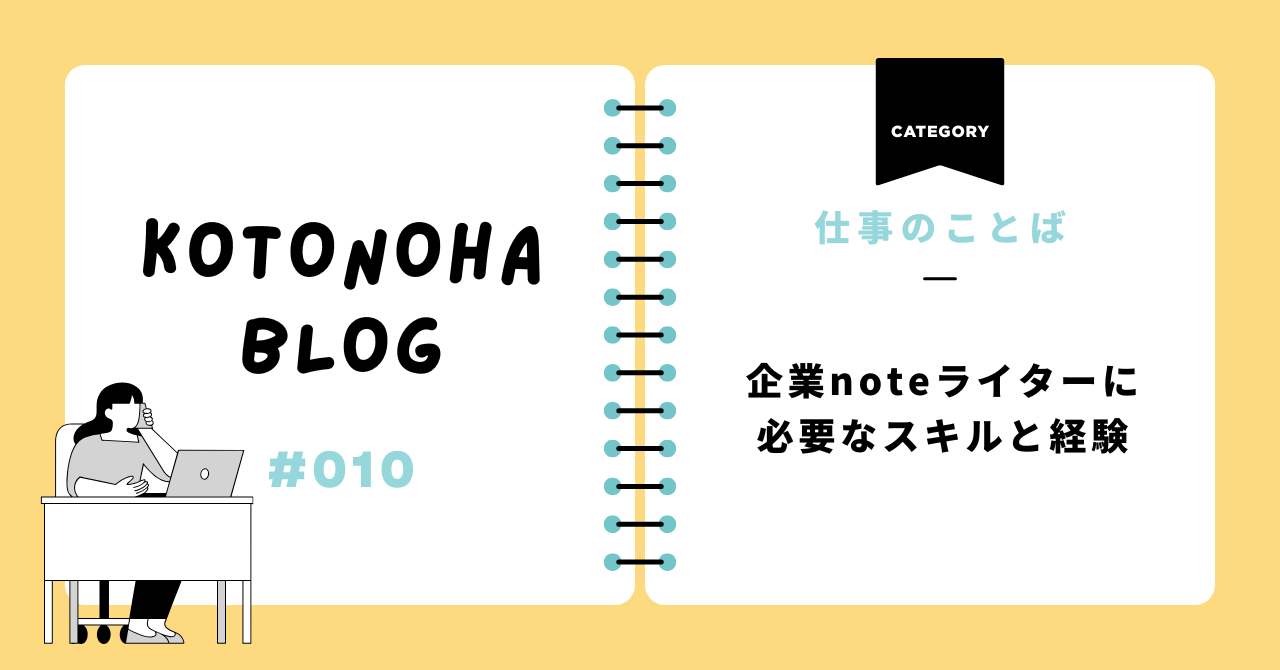
まとめ:AIは便利だけど、人間の手が必要
ChatGPTは企業note作成を効率化してくれる強力なサポートツールですが、AIだけで完結させるのは危険です。
構成案作成や下書き生成、アイデア出しなどは時間を短縮できますが、企業のトーンや事実確認、コンプライアンスのチェックは人間が行う必要があります。
AIに任せられる部分と人間が手を加える部分をうまく分け、質の高い記事を作っていくことが大切です。