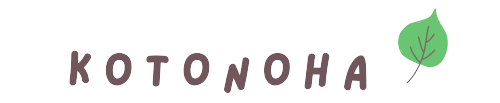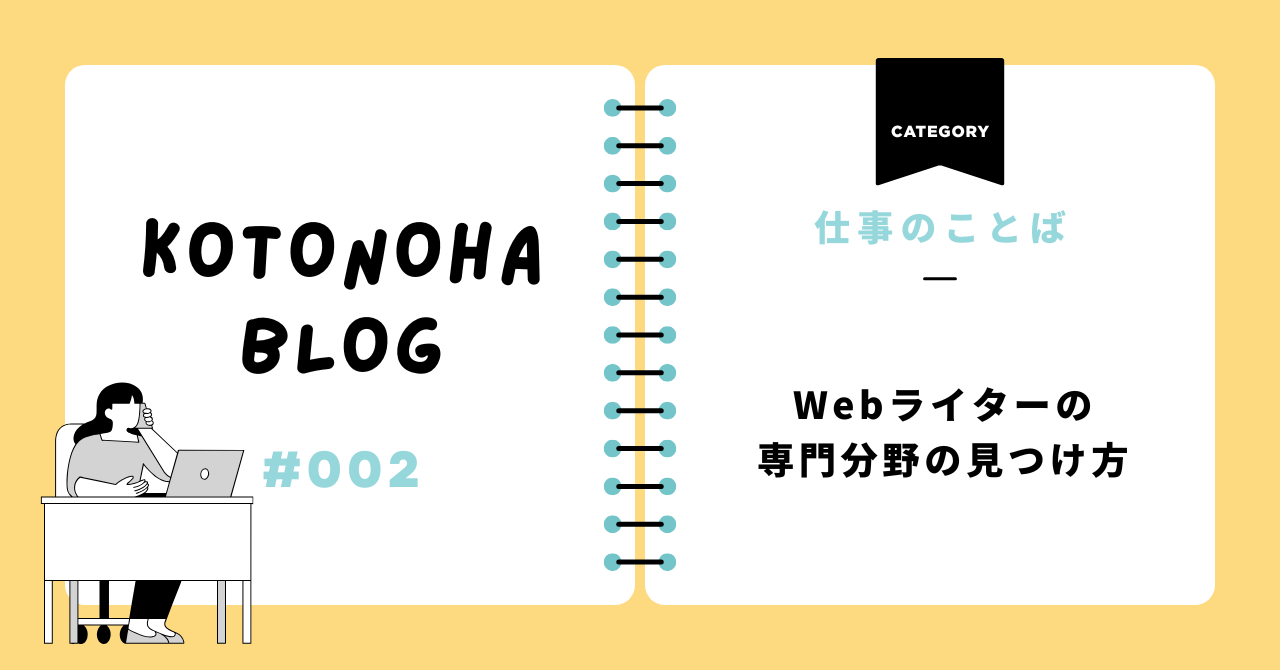「専門分野って、どうやって決めればいいんだろう…」
「何でも書けます、じゃダメなのかな…」と悩んでいる人は多いのではないでしょうか。
私もライターを始めた頃は同じで、専門を決められずに思うように仕事が見つからず、単価も上がらないのが悩みでした。「何でも書けるライター」を目指していたのに、なかなか結果が出ない日々。
でも、専門分野を持つようになってから、仕事の質も単価も大きく変わりました。今では金融ライターという肩書きを持ちながら、育児や働き方など、さまざまなジャンルの記事を書いています。
この記事では、Webライターが専門分野を見つけるための具体的な方法と、迷ったときに使える選び方の基準をお届けします。
なぜWebライターに専門分野が必要なのか
まず、専門分野がなぜ必要なのか、理由を整理してみましょう。
クライアントから選ばれやすくなる
クライアントが求めているのは、「その分野に詳しいライター」です。
たとえば、美容系のメディアを運営しているクライアントが、2人のライターを比較したとします。
Aさん: 「美容、金融、不動産、旅行など、幅広く執筆できます」
Bさん: 「美容ライター歴3年。スキンケアと化粧品レビューが得意です」
どちらが選ばれるでしょうか。圧倒的にBさんですよね。
専門分野があることで、「この人に任せれば安心」という信頼感が生まれます。
単価が上がりやすい
専門性があるライターは、リサーチ時間が短く、質の高い記事を書けます。だからこそ、クライアントも高単価で依頼してくれます。
私自身、専門分野を持つ前は文字単価1円前後でしたが、専門性を確立してからは文字単価4円以上の案件が中心になりました。同じ執筆時間でも、収入が4倍になったわけです。
継続案件につながりやすい
専門分野があると、同じクライアントから継続的に依頼されることが増えます。
「このジャンルならこの人」と覚えてもらえるので、新規営業をしなくても仕事が入ってくるようになるんですよね。実際、私も今では8割以上が継続案件やリピート依頼です。
記名記事の実績が作りやすい
専門分野を持つと、記名記事(ライター名が掲載される記事)を任されることが増えます。
一般的な記事はライター名が出ないことが多いですが、専門性の高い記事では「〇〇専門ライター △△」のように、名前と専門分野が明記されることがあるんです。
記名記事が増えると、それ自体がポートフォリオになり、次の案件獲得にもつながります。実際、私も金融分野で記名記事を書くようになってから、「あの記事を書いた方ですよね」と声をかけられることが増えました。
専門性を持つことで、ただの「書く人」から「その分野の専門家」として認識されるようになるんです。
ライティングが楽になる
専門分野が決まっていると、リサーチが蓄積されていくので、記事を書くスピードがどんどん速くなります。
最初は1記事に2~3時間かかっていたものが、専門性が深まるにつれて1時間前後で書けるようになる。効率が上がれば、時給も上がるということです。
専門分野が決まらない人の3つの共通点
専門分野を決められない人には、実はある共通点があります。
「好きなこと」だけで選ぼうとしている
「好きなことを仕事にしたい」という気持ち、よくわかります。でも、好きなことが必ずしも専門分野になるとは限らないんです。
たとえば、旅行が大好きでも旅行ライターの案件は競合が多く、単価も低め。一方で、自分が詳しい「子連れ旅行」や「格安旅行術」に絞ると、ニッチで需要のある専門分野になります。
好きなことをベースにしつつ、「どう切り取るか」が大事なんですよね。
完璧に詳しくないとダメだと思っている
「専門家レベルじゃないと書けない」と思い込んでいる人、多いと思います。
でも、Webライターに求められるのは、「専門家の知識」ではなく、「読者にわかりやすく伝える力」です。
実際、私も最初から専門家だったわけではありません。書きながら学び、リサーチを重ねる中で、自然と専門性が深まっていきました。
「少し詳しいレベル」で十分スタートできるんです。
一つに絞れないと思っている
「専門分野って一つじゃないとダメなの?」と不安になる人もいるかもしれません。
実は、専門分野は複数持っていて大丈夫です。むしろ、2〜3つの専門分野を持つことで、案件の選択肢が広がり、収入も安定します。
私自身も、宅建士やFP2級、証券外務員1種の資格を活かし、「金融」「不動産」「保険」の3つを主な専門分野にしています。
迷ったときに使える3つの選び方基準
ここからが本題です。専門分野を選ぶときに使える、具体的な3つの基準をお伝えします。
基準1:経験×興味があるか
専門分野を選ぶときに最も重要なのが、「自分が経験していて、かつ興味がある分野」です。
経験があれば、リサーチしなくても書ける部分が多く、説得力のある記事になります。興味があれば、継続的に学び続けられるので、専門性がどんどん深まります。
具体例:
- 元営業職なら「BtoB営業」「営業ツール」
- 子育て中なら「育児グッズ」「幼児教育」
- 転職経験があるなら「転職ノウハウ」「面接対策」
- 趣味で筋トレしているなら「フィットネス」「プロテイン」
「何を書けばいいかわからない」という人は、まず自分の人生を振り返ってみてください。
- 今までどんな仕事をしてきたか
- どんな趣味や習慣があるか
- 何に時間やお金を使っているか
- 人からよく相談されることは何か
この中に、専門分野のヒントが必ず隠れています。
私の場合は、保有資格を活かして「金融」分野から始め、そこから「不動産」「保険」と関連分野に広げていきました。
基準2:市場の需要があるか
どんなに詳しくても、需要がなければ仕事になりません。逆に、少し知識がある程度でも、需要が高ければ専門分野として成立します。
需要を調べる方法は、以下の通りです。
クラウドワークスやランサーズで、そのジャンルの案件がどれくらいあるかチェック。単価や募集頻度も確認。
ラッコキーワードやGoogleキーワードプランナーで、そのテーマがどれくらい検索されているか確認。
案件に対して応募者が多すぎる分野は初心者には厳しい可能性があるほか、ニッチすぎて案件が少なすぎる分野も避けた方が無難
たとえば、「金融」は需要が高いですが、競合も多く、専門知識も必要です。一方で、「金融×初心者向け」「金融×主婦目線」のように切り口を変えると、ニッチで戦いやすくなります。
需要と競合のバランスを見ながら、「自分が戦える場所」を見つけることが大事です。
基準3:継続的に学べるか
専門分野は、一度決めたら終わりではありません。むしろ、継続的に学び続けることで、専門性がどんどん深まっていきます。
だからこそ、「この分野なら、ずっと学び続けられそう」と思えるかどうかが重要です。
チェックポイント:
- その分野の本を読むのが苦にならないか
- 関連するニュースやブログを自然とチェックしているか
- その分野について話すのが楽しいか
もし「勉強するのが辛い」「情報を追うのが面倒」と感じるなら、それは専門分野として向いていないかもしれません。
私がライティング分野を選んだのは、「文章を書くこと」「伝えること」について学ぶのが純粋に楽しかったからです。書籍を読んだり、他のライターの記事を読んだりするのが全く苦にならない。だからこそ、続けられているんだと思います。
専門分野を見つける具体的なステップ
ここまで読んで、「なんとなくイメージできてきた」という人も多いと思います。ここからは、実際に専門分野を見つけるための具体的なステップをお伝えします。
ステップ1:自分の「経験・興味・強み」を書き出す
まずは、紙やスマホのメモアプリに、自分の経験や興味を思いつく限り書き出してみましょう。
書き出す項目:
- 今までの仕事や職歴
- 趣味や習慣
- 資格や勉強してきたこと
- 人生で苦労したこと、乗り越えたこと
- 人からよく相談されること
- お金や時間をかけていること
完璧に整理しなくて大丈夫です。思いつくままに、どんどん書き出してください。
ステップ2:需要があるかリサーチする
書き出したテーマの中から、「これなら書けそう」と思うものを3〜5個ピックアップします。
そして、それぞれのテーマについて、以下をリサーチしましょう。
- クラウドソーシングサイトで案件数を確認
- Googleで検索ボリュームをチェック
- 競合ライターがどれくらいいるか調べる
この時点で、「需要はあるけど、競合が多すぎる」と感じたら、もう少しテーマを絞り込んでみてください。
たとえば、「美容」なら「敏感肌向けスキンケア」、「転職」なら「30代女性の転職」、「投資」なら「初心者向けつみたてNISA」のように、より具体的なターゲットに絞ることで、戦いやすくなります。
ステップ3:まずは1つの分野で10本書いてみる
専門分野を決めたら、まずはその分野で10本記事を書いてみましょう。
クラウドソーシングで案件を受けてもいいですし、自分のブログで書いてもOK。とにかく、実際に書いてみることが大事です。
10本書くと、以下のことがわかってきます。
- この分野、本当に自分に合っているか
- リサーチが苦にならないか
- 継続して書き続けられそうか
もし「やっぱり違うな」と感じたら、別の分野を試してみてください。試行錯誤しながら見つけていくのが、専門分野を確立する一番の近道です。
ステップ4:ポートフォリオに専門性をアピールする
専門分野で10本以上記事を書いたら、ポートフォリオを作りましょう。
ポートフォリオには、以下を盛り込むと効果的です。
- 専門分野の明記(例:「育児×働き方専門ライター」)
- これまでの執筆実績(URLや記事タイトル)
- 自分の強み(例:「3児の母として、リアルな育児体験を記事にできます」)
専門性が明確になると、クライアントからの信頼度が一気に上がります。
専門分野が決まらなくても大丈夫
ここまで読んで、「やっぱり決められない…」と思った人もいるかもしれません。
でも、安心してください。専門分野は、最初から完璧に決まっている必要はありません。
むしろ、書きながら見つかることの方が多いんです。
私も最初は「何でも書けるライター」を目指していましたが、案件をこなしていく中で、自然と「この分野が得意かも」「この分野、楽しい」と気づいていきました。
大事なのは、まず動き出すこと。
完璧を求めて立ち止まるより、「とりあえずこの分野で書いてみよう」と一歩踏み出す方が、専門分野は見つかりやすいです。
まとめ:専門分野は「育てる」もの
専門分野は、最初から持っているものではなく、書きながら「育てていく」ものです。
- 経験と興味があるか
- 市場の需要があるか
- 継続的に学べるか
この3つの基準を軸に、まずは1つの分野で10本書いてみてください。
書いているうちに、「これが自分の専門分野だ」と自然に感じられる瞬間が必ず来ます。
Webライターとして長く続けていきたいなら、専門分野は必ず武器になります。焦らず、自分のペースで、少しずつ専門性を深めていってくださいね。
あなたの専門分野が見つかる日を、応援しています。